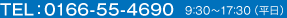メディア旭川 連載記事
世論遊論 『酒と泪と男と司法試験』
第130杯「リーガルマインド(法的思考力)」
長男が、司法試験予備試験の短答式に合格し、論文式を受験しました。
論文式試験では、結論に至るまでの法的思考過程を示す必要があります。端的に言えば結論だけではなく理由も書くということです。今でもそうだと思います。
論文式の問題を解くとき、複数の論点があったとします。論点ごとに学説・判例をきっちり抑え、論理的に間違いのないように学説を組み合わせてから、結論を出そうとする人がいます。ぼくもそうだったと思います。
裁判では、当事者が主張立証を尽くした後、裁判官は裁判に現れたすべての事実や証拠を取捨選択し、総合的に考慮して結論を出すという「自由心証主義」という建前が採用されています。この建前からすると、前記の結論の出し方は正しいと思われますが、司法試験に合格するという観点からは時間のかかるやり方です。日常の学習において、ある論点について学説・判例を理解し、それから次の論点を学習するというのでは、論点を一通り学習するのに多大な時間と労力を費やします。答案上でも学説の対立・論理的整合性に配慮するあまり、前提部分の論述に時間を費やし、肝心部分、メイン部分にたどり着けなかったり、たどり着いても論述が不十分になってしまうことがあります。また、論理的なのですが、形式的になりすぎて非常識な結論を導いてしまうこともあります。
こうしたロスやミスを防ぐためには、自分の常識を信じ、まず直感で常識的な結論を出して、それに合わせて、与えられた事実や事情をあれこれ検討して取捨選択し、論理的にある程度スジが通るように理由付けするのが合理的で、ミスも少なくなると思います。法律学は自然科学ではないので、論理的に完全に誤りということは起こりにくいし、司法試験は学者になるための試験ではなく、実務家になるための試験だからそれで良いと思います。長男にも、そうアドバイスしています。
実際の裁判でも、「自由心証主義」の建前にもかかわらず、裁判官は、まず、常識的な結論で心証形成をした上で、理由は後付けで考える、事実や証拠の取捨選択は後付けとしていると思われます。論理的には筋は通っているのに敗訴してしまうことがあるのは、裁判官の感覚で常識的な結論を出してから、理由付けをしているからだと思います。その意味で、裁判は、裁判官の常識、いうなれば裁判官の主観・感覚に左右されるものといえるでしょう。