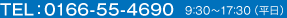メディア旭川 連載記事
世論遊論 『酒と泪と男と司法試験』
第129杯「うどん」と「そうめん」の話
麺類の中で一番好きなのは、実は、うどん系です。山越(やまこし)という、カマタマ(卵かけ釜上げうどん)発祥の店とされる店が香川県にあり、「ことでん」に乗って、綾川という駅まで行き、そこからタクシーを呼んで片道1500円、往復3000円かけて一杯150円のカマタマを食べに行ったことがあります。
長崎県の五島うどん、讃岐うどん、徳島県の半田そうめんあたりを取り寄せて食べています。半田そうめんは、細うどん位の太さがある。少なくとも、以前は、あったように思います。「そうめん」ではなくて「うどん」なのではないか。この半田そうめんの謎は、以前から抱いていた疑問でしたが、調べてみると、うどん・ひやむぎ・そうめんは太さで分類されており、JAS規格の「乾麺類品質表示基準」では、機械で切って製麵する場合は直径1.3㎜未満がそうめん、1.3㎜以上1.7㎜未満がひやむぎ、1.7㎜以上がうどんと定められているようです。半田そうめんは、製麺所によって、太さが異なりますが、少なくとも1.3㎜以上の太さがあるものと思います。はたして「そうめん」と名乗ることができるのでしょうか。さらに調べてみると生地を細長く引き延ばして作る「手延べ」の場合は、直径1.7㎜未満のものが「そうめん」と「ひやむぎ」、それ以上のものは「うどん」とされています。つまり、機械を使わない「手延べ」の場合は、「そうめん」と「ひやむぎ」の区別がなく、1.7㎜未満であれば、「そうめん」と名乗ることができるのです。半田そうめんは「手延べ」なのでしょう。半田そうめんの謎は、一応解決しました。半田そうめんの中には、直径1.7㎜以上のものがあったような気がしますが、規格に合わせて細くしたのでしょう。
飲んだ後の締めに、居酒屋で「にゅうめん」を注文することがあります。ラーメンは重たいので躊躇しますが、「にゅうめん」ならいいかという感じ。温かいダシで食べるそうめんですが、なぜ「にゅうめん」というのでしょうか。これも調べてみると、奈良県が発祥の郷土料理で「煮麺」と書くそうです。奈良県三輪地方の特産品として三輪そうめんがあり、そうめん特産地の郷土料理ということになります。なお、半田そうめんは、三輪そうめんの製法を阿波半田に持ち込んで作られるようになったもののようです。三輪そうめんの半田版ということで半田そうめんと名乗っているのかも知れません。