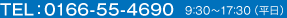メディア旭川 連載記事
世論遊論 『酒と泪と男と司法試験』
第121杯「若者とそうでない人」
調停や裁判の手続きで、依頼者と一緒に裁判所に出頭することがあります。その際、依頼者が「担当裁判官が若くてびっくりした」と、言うのをよく聞きます。調停や裁判で担当裁判官が1人の場合、裁判官としての経験が最低5年はあるので30歳は過ぎていることが通常です。
世間一般的に30歳が若いのかというと、必ずしもそうではなく、むしろ、30歳は、若者ではなくなる、オジン・オバンになってしまう分水嶺の年齢と思います。ぼくが大学生のころは、留年して、なかなか卒業しない24,5歳の先輩を「もう若くない」と思っていましたし、同世代もしくは年下の女性が「30歳を超えた人と付き合っている・交際している」と聞くと、なぜ、そんなオヤジと交際するのか不思議に思うなど、30歳以上の男性は、とんでもなくオヤジだと思っていました。
ぼくは、33歳で司法試験に合格しているので、司法試験受験時代に30歳になってしまうのですが、30歳になってしまった当時、精神的に甚大なショックを受けました。40歳、50歳になったときは、30歳になったときほどのショックはありませんでした。30歳になる=若者ではなくなる・青春も完全に終了ということで、一抹の寂しさがあったのだと思います。したがって、世間一般的には30歳を超えた人は若者ではなく、少なくとも「若くてびっくり」ということにはならないと思います。
「裁判官が若くてびっくり」と言う人は、自分と比べて随分と若いという意味で言っているのであり、裏を返せば、自分が「相当年齢を重ねた、年を取った」旨の発言であって、当の本人はそのことをあまり意識しないで発言しているのだと思います。
交通事故で傷害を負い、後遺症障害が残って労働能力に支障が生じた場合、将来の収入が減少するとしてその分の損害(逸失利益)を算出して請求しますが、その過程で稼働可能年齢とされる67歳までの年数と、平均余命の半分の年数のどちらか長い方を採用して算出します。若年者は67歳までの年数の方が、高齢者は平均余命の半分の年数の方が長くなります。ぼくは57歳となり、若者だったのは四半世紀以上も前のことになりました。そして、いつの間にか平均余命の半分の年数の方が長くなってしまいました。逸失利益の計算の上では、高齢者の方に分類されます。これに気がついたときは、さすがにびっくりし、余命期間、健康に留意して稼働しようと思いました。