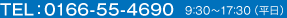北海道経済 連載記事
2016年3月号
第72回 裁判での供述は冷静に
法衣の裁判官が見下ろし、厳粛な空気が漂う法廷での供述。緊張、興奮のあまり不用意な言葉を口走ってしまうことも…。小林史人弁護士は「必要なことだけ簡潔に語るべき」とアドバイスする。(聞き手=本誌編集部)
民事訴訟では、事件本人(原告、被告)や証人が法廷内の証言台に座り、双方の代理人や裁判官からの質問(尋問)に答えて、知っている内容を口頭で供述することがあります(証人の場合にはとくに「証言」という用語が用いられます)。
原告と被告が裁判の途中で和解したり、裁判官が有力な物証があると判断した場合には、尋問を経ないで裁判が終了することもあります。そうでなければ尋問が行われ、事件本人・証人の供述(人証)が、物証と並んで裁判の勝敗を左右する要素となります。
尋問は、これを申請した側の代理人による主尋問、その相手側による反対尋問という順番で行われます。裁判官の判断で、裁判官が尋ねる補充尋問や、再主尋問・再反対尋問が行われることもあります。主尋問でどのような質問が行われるのかは、尋問を受ける側に事前に知らされ、主尋問、反対尋問にどれだけの時間をかけるのかも事前に決められます。
たいていの人は、証言台に立てば緊張します。知っていることや感じていることをうまく述べられないかもしれません。このため弁護士は、依頼者である事件本人や、裁判で有利な証言をしてくれそうな証人と事前に打ち合わせをします。まず、尋ねる内容はあらかじめ伝え、どう答えるのかを確認しておきます。相手側の代理人が行う尋問についても、問われる内容は予測がつきますので、どう答えるのかを整理しておきます。また、私の場合はよく知らないこと、よく覚えていないことについては、「知らない」「覚えていない」と述べるよう勧めています。推測で供述して、結果的に虚偽の供述をしたり、相手方の尋問で挙げ足を取られないようにするためです。また、事件本人や証人が述べる内容に矛盾があり、反対尋問で追及されそうなときは、先に主尋問で述べさせるようにします。
なお、証言台には尋問の手控えを持ち込めませんので、事実関係等、供述ないし証言すべき事項はあらかじめ記憶しておかなければなりません。
さて、法廷で行われる「本番」の尋問で、弁護士が期待した通りの証言・供述が得られるとは限りません。自分の主張を裁判官に理解してもらいたいという気持ちや、争っている相手に対する恨みが強すぎたり、反対尋問での予想外の問いに動揺したりして、質問されていないことを延々と語る人がいます。
供述の内容は、たとえそれが尋問からずれていたとしても尋問調書に盛り込まれ、判決を左右する材料になり得ます。とくに、こちら側に有利な判決が見込まれる状況においては、相手側に「逆転」の余地を与えないためにも、問われたこと以外について不用意に述べるべきではありません。
さて、事件本人が法廷で虚偽の供述をすれば、10万円以下の過料を課されます(民事訴訟法209条)。一方、証人が虚偽の証言をすれば偽証罪に問われ、3月以上10年以下の懲役を科されます(刑法169条)。裁判では事件本人よりも証人の供述の方が証拠としての価値が高いとされているため、故意に事実と異なることを述べた場合の責任は、事件本人よりも証人の方が重くなり、証人の虚偽の供述には刑罰が科されます。