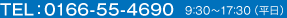北海道経済 連載記事
2015年12月号
第69回 裁判では真相は究明されない
確定した判決が覆され、裁判がやり直されるケースが相次いでいる。今回の「法律放談」では、刑事裁判が必ずしも真実の究明という役割を果たしていない問題について。(聞き手=本誌編集部)
いわゆる「東住吉女児焼死事件」について、10月23日に大阪高裁が再審を決定し、2人の元被告が約20年ぶりに自由の身となったことが大々的にニュースで取り上げられました。少し前の10月16日には、10代女性に対する強姦などの罪で2011年に懲役12年が確定し、服役していた男性について、「被害者」が嘘の証言をしていたことを認めたことを受けて再審が行われ、無罪判決が下されました。
この数年間のうちに多くの刑事事件で裁判がやり直され、いったんは有罪が確定したはずの「犯人」が、一転して無実になるケースが相次いでいます。有罪となって服役した人が被った不利益は計り知れません。強姦罪で服役していた男性は、冤罪を見逃した責任が国と大阪府にあるとして、近く賠償を求めると報じられています。
相次ぐ冤罪の一因は、裁判が必ずしも真実の究明という役割を果たしていないことにあります。私個人も刑事事件の被告人を弁護しながら、それを強く感じることがあります。
密室内で被害者が死亡したある重大な刑事事件で、犯行当時室内にいたXとYが起訴されました。目撃者はXの子(当時6歳)だけ。Yが犯行に関与した上、主導した主犯なのか(Xは当初はYの単独犯と供述していたが、供述をこのように変えた)、Xの単独犯でYは犯行に関与していないのか(Yの供述)が、裁判の主要な争点となりました。
警察は事件直後、Xの子の供述をもとに調書を作成しました。供述内容はXが実行犯で、Yは犯行に関与していないことを示していました。
ところが、この調書は警察が作成したものであるにも関わらず、裁判では証拠として採用されませんでした。刑事訴訟法第321条1項3号の規定により、警察が作成した被告人以外の供述調書は、供述した人が病気や出国などのために公判で供述できない場合に限って裁判の証拠になると定められているためです。
Xの子は事件から約10ヵ月後に法廷で証言しましたが、幼い子への心理的な悪影響を考慮し、尋問事項に制限が設けられ、尋問時間も短時間しか認められませんでした。約10ヵ月が経過し、記憶もあいまいになっていたのか、私がYの関与について尋ねても、その時点ではもう事件直後の供述のような証言は得られませんでした。裁判官はYが犯行に関与したと断定して、Xよりも重い実刑判決を下しました。
前述した刑事訴訟法の条文は、法廷外での供述を記録した書面よりも、反対尋問による吟味が可能な法廷での供述を重視すべきという刑事訴訟法の基本的な考え方を反映したものですが、この規定のために、唯一の目撃者であるXの子が目撃したものを正確に語った可能性が大きい事件直後の供述は省みられず、裁判は真実から遠ざかってしまいました。
裁判所には抱えている多くの訴訟の審理を円滑に進める役割があり、すべての材料を証拠に採用するのは非現実的です。しかし、刑事訴訟法の条文を機械的に運用した結果、真実の究明が疎かになるようでは、本末転倒ではないかと思います。