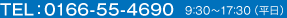北海道経済 連載記事
2015年7月号
第64回 「市民感覚」判決にどこまで反映?
庶民がもつ「市民感覚」をどこまで裁判の判決に反映するのかは、司法制度にとり大きな課題であり、裁判員制度が導入されたのも、それがひとつの目的だった。今回の「法律放談」はこの「市民感覚」に注目する。(聞き手=本誌編集部)
韓国では、多くの犠牲者を出した「セウォル号沈没事故」から約1年後の今年4月、この事件の裁判の二審で、船長に「未必の故意による殺人罪」で無期懲役の判決が言い渡されました。一審では船長について殺人罪が認められず、遺棄致死罪などで懲役36年の有罪判決が言い渡され、韓国国内で反発が強まっていました。二審判決は厳罰を求める世論に歩み寄ったかたちです。これとは対照的に、5月22日に下されたいわゆる「ナッツリターン事件」の二審判決では、離陸前の機内サービスに腹を立て、担当の乗務員を降ろすために旅客機を搭乗口に引き返させた大韓航空の副社長に、執行猶予つきの有罪判決を言い渡しました。「離陸前の進路を変更させた行為も航路変更罪に該当する」との一審の判断を覆すことで、事件直後の韓国国内の激しい世論とは距離を置き、冷静な判断を示したと言えます。
日本の裁判官については、憲法は「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される」と定めていますが、現実にはその判断に世論が一定の影響を及ぼすことがあります(光市母子殺害事件など)。また、裁判員裁判が導入され、対象となる事件の一審判決に市民感覚が反映されるようになりました。もっとも、最近、一審の裁判員裁判で死刑判決が言い渡され、高裁がこれを覆した二つの裁判について、最高裁が高裁を支持する決定をしました。市民感覚も反映した「死刑」の判断に、上級庁の裁判官が「ノー」を突きつけたことになります。
このうち一つは、2009年に女子大生を殺害した男が強盗殺人などの罪に問われた裁判です。殺された被害者は1人ですが、一審では被告がこの事件の前後に複数の強盗強姦事件を起こしていたことも理由に死刑判決が言い渡されました。しかし高裁はこれを覆して無期懲役を選択。最高裁も「死刑の適用は慎重さと公平さが求められる」「過去の裁判例をもとに検討した結果を共通認識として議論すべき」などと指摘した上で、高裁を支持しました。つまり、殺された被害者が1人の場合に死刑に処すれば、他の類似事件と比較して重すぎると判断したわけです。
一般市民の感覚は被害者寄りであり、時として3800年前の古代バビロニアのハムラビ法典のような「目には目を、歯には歯を」といった同害報復を肯定し、江戸時代の忠臣蔵のような仇討ちを美徳とする方向に流れがちです。ある意味、人間の本能なのでしょうが、それをすべて認めてしまえば日本の司法制度も大昔のハムラビ法典のようになってしまいます。とくに死刑は後戻りができない刑罰であり、裁判員裁判で言い渡された極刑の判断に、高裁や最高裁がブレーキをかけるのは自然な流れと言えるでしょう。
しかし、だとすれば死刑の可能性もある凶悪犯罪の裁判はプロの裁判官が担当するべきで、「市民感覚」を取り入れる意義はあまりないことになります。窃盗や詐欺といった日常的な犯罪の裁判にこそ「市民感覚」を取り入れるべきであり、裁判員裁判の対象が法定刑の重い一定の犯罪の事件に限定されていることの妥当性が問われているとも言えます。