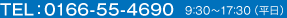北海道経済 連載記事
2025年8月号
第185回 無期懲役の衝撃
一昨年、日本国内では17件の無期懲役判決が確定した。有期の刑罰の場合は、社会復帰が見通せるが、無期の刑罰では見通せない。今回は、無期判決が有り得る場合の弁護人の行動について考える。 (聞き手=本誌編集部)
刑法が改正され、懲役刑と禁固刑の区別が廃止され、拘禁刑に統一されました。刑務作業が義務か否かの違いだけで、禁固でも任意に刑務作業に従事する者が多数で、実質的に同じだからです。
他方、刑期については、有期と無期とでは大きな違いがあります。無期の刑罰は事実上、終身刑に近い刑罰として機能しているため、社会復帰が見通せません。先日、旭川刑務所に収監されている受刑者から依頼を受け、面会しに来たという弁護士と話す機会がありました。聞けば、その受刑者の刑事事件の裁判を担当し、裁判では無罪を主張したものの、一審判決では当時の有期懲役の上限である懲役20年の判決が言い渡され、検察、弁護双方が控訴し、控訴審での判決はさらに厳しい無期懲役の判決。上告しても判決が覆ることはなく、今から20年以上前に無期懲役の判決が確定し、旭川刑務所に収監されました。
担当した事件で無期懲役の判決が言い渡されたことは、私には経験がありません。その弁護士いわく「弁護士人生で最大の衝撃だった」とのことです。一審では有期だったのに控訴審では無期となったのだから衝撃もなおさら大きかったと思います。単なる職務上のできごとの一つとして片づけることができなかったからか、その弁護士は、現在に至るまで受刑者の家族をサポートし続け、受刑者とは連絡を取り合っているとのことでした。
受刑者は問題の事件の実行犯ではなく、裁判では、事件の言わば黒幕として、実質的な正犯として犯罪を問えるかが争点となったようです。弁護人と受刑者が無罪を主張した経緯は分かりません。実行犯ではないので無罪主張も当然なのかもしれません。ただ、自分だったら、無期懲役が有り得る場合、無罪主張を躊躇すると思います。
裁判で被告人の有罪判決が確実な状況で、あくまでも無罪を主張するべきなのか、早々に罪を認めて反省していることを示すべきなのかは、とくに無期の刑罰が有り得る場合、難しい問題です。建前上、量刑は被告人が罪を認めているか否かによって左右されませんが、現実には裁判官の心証形成に大きな影響を与えるだろうと思います。
最近、社会的な注目を集めた刑事事件の被告人となった若者2人のうち1人が、一審で罪を認め、懲役23年の有罪判決を言い渡され、控訴しなかったため刑が確定しました。これは、何としても無期懲役だけは避けたいとの考えが働いた結果かもしれません。制度上、有期刑は刑の3分の2が執行された時点で仮釈放の見込みがあります。無期懲役も仮釈放の可能性は残っていますが、実際に無期懲役の受刑者が仮釈放されるケースは全国で年に5人(2023年)と少数で、仮釈放までに刑務所にいた期間は30〜35年が1人、35〜40年が3人、45〜50年が1人と長期に及んでいます。懲役23年ならその3分の2は16年弱。仮釈放なら30代で出所できる、まだ人生をやり直せるとの判断が働いて罪を認めたとしても、不思議ではありません。
被告人が無罪を強く主張している場合、無期の刑罰のリスクがあるからという理由で罪を認めるよう説得するのは弁護人として問題のある行動です。厳しい判決が言い渡されるリスクを考えながら、法廷では被告人の主張を補強するよう努めるしかないでしょう。