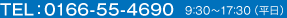北海道経済 連載記事
2025年5月号
第182回 真相究明妨げる人質司法
刑事裁判には、有罪が確定するまでは被疑者や被告人を罪を犯していない人として扱うとの原則(無罪推定原則)があるが、現実の裁判制度は厳しい。容疑を認めない被疑者・被告人は長期間にわたり拘束される。今回は日本の刑事裁判制度の問題と指摘される「人質司法」について。 (聞き手=本誌編集部)
現在の日本の司法制度では、容疑を否認したり黙秘したりしている被疑者・被告人が身柄を長期間にわたり拘束される傾向があります。早期に釈放されたいとの心理につけこみ、被疑者・被告人から自白を引き出すのが狙いとの指摘があります。
元厚生労働次官の村木厚子氏は、無実の罪で逮捕され、容疑を頑なに否認したため半年近く勾留された経験を持ち(その後、検察が証拠を捏造していたことが判明)、現在は人質司法をなくすための活動に従事しています。日産のカルロス・ゴーン元会長も数ヵ月にわたり拘束され、弁護人や海外のマスコミを通じて日本の司法の問題を指摘していました(その後、保釈中に楽器ケースに隠れて海外に逃亡)。
被疑者・被告人が身柄を拘束されている間は仕事ができず、家族とも引き離され、無罪判決を得て釈放されたとしても、その時点では生活が立ち行かなくなっているかもしれません。大半の刑事裁判で有罪判決が言い渡されることから、「容疑を認めて、実刑判決さえ回避できればいい」との考えも成り立ちます。
被疑者が起訴されて被告人となれば、その時点で検察は十分な証拠を確保しており、保釈しても裁判に影響しないはずですが、被告人が容疑を否定したり黙秘したりしていると、裁判官は保釈をほとんど認めません。
刑事裁判では「人質司法」の現実の下、真相究明がないがしろにされていると感じることがしばしばあります。被告人の人権を著しく侵害する冤罪を防ぐためには、真相をしっかりと究明した上で判決を言い渡すべきことは当然です。犯罪事実に争いのない裁判でも、人質司法の弊害は見られます。身柄の自由を早く取り戻したい被告人と、早期に裁判を終わらせたい裁判所・検察の利害が一致して、情状面の審理がおざなりにされがちです。最初の期日で40分程度の審理を経てその期日のうちに執行猶予付きの有罪判決が言い渡されることもあります。
このような裁判では、裁判官は初めて証拠を見てから40〜50 分で判決を言い渡すのですから、情状に関する事実を十分に審理することは時間的に難しい場合もあります。被告人が別の人物に誘われて犯罪に加わったとしましょう。被告人は主犯ほど強く非難されるべきではないはずですが、裁判所は時間をかけて被告人が犯罪を主導したのか、受け身で加わったのか、どんな役割を果たしたのかを解き明かそうとはしません。被告人の言い分は信用できない、被告人も重要な役割を果たしたと言い切るだけです。迅速な裁判で執行猶予付きの有罪判決が言い渡されれば、被告人が自由を早期に回復し、社会に戻れることも事実なのですが、情状に関する事実の審理を軽視する裁判所の姿勢には危うさを感じます。
裁判所が起訴後の被告人の保釈に前向きになれば、こうした状況は改善されるはずです。裁判は長期化し、関係者の手間は増えるかもしれませんが、情状に関する事実についても量刑に影響するのですから、ある程度時間をかけて証拠を吟味して認定するべきなのではないかと感じています。