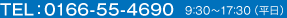北海道経済 連載記事
2025年4月号
第181回 執行猶予を得るには
刑事事件での弁護人の役割は、被告人が罪を認めていないのであれば無罪判決を獲得すること、罪を認めているのであればできるだけ刑を軽くすること。執行猶予を付し得る場合は、執行猶予の獲得が被告人の関心も高く、現実的な目標となる。今回は、執行猶予について。 (聞き手=本誌編集部)
刑事裁判では、判決内容が3年以下の懲役刑・禁錮刑の場合に裁判官が情状に応じて1〜5年の期間、刑の執行つまり被告を刑務所に入れるのを猶予することができます。これが執行猶予です。法定刑が3年を超える罪に執行猶予を付けるには、情状酌量で減軽して刑の下限を3年以下にする必要があり、たとえば殺人罪(法定刑は5年以上)は、被害者から長期間に渡り虐待を受けていたなど特別な事情がある場合を除いて、執行猶予はつきません。また、執行猶予は基本的に初犯が対象で、累犯は執行猶予の可能性が低くなります。
執行猶予を付けるかどうかは裁判官が決めることですが、検察官の求刑が3年以下の場合、検察官は、表向きは実刑を求めているものの、内心は執行猶予に付してもかまわないとの意思と考えることもでき、実際、執行猶予の付いた判決に対して控訴することは、まず、ありません。逆に3年を超える求刑をしたにもかかわらず、3年以下に減軽され、かつ執行猶予が付いた判決の場合、控訴されることもあります。
刑事事件の被告人にとって、執行猶予が付くのか、付かずに実刑判決となるのかは重大な問題です。接見の際、「執行猶予を絶対に付けてくれ」と言われることもあります。私としては「可能性は高いと思うが『絶対』はないよ」と言うしかありません。
裁判では弁護人からの被告人尋問の中で「なぜ犯行に及んだのか」「どう行動するべきだったのか」「再犯をどう防ぐのか」などを述べてもらい、真摯に反省していることを裁判官に伝えるようにします。また、被害者との示談が成立するように努力します。そうすれば、執行猶予を付けてもらえることが多いです。
司法修習生時代に、意外な実刑判決を見た記憶があります。駐車中の車のガラスを携帯用の小さなハンマーで割って乗り込み、車内にいたところを窃盗(車上荒らし)未遂で現行犯逮捕された事案でした。被疑者が「車の中で休んでいただけ」と窃盗の故意を否認したところ、器物損壊でも逮捕され、これについても「軽く叩いただけでガラスを割るつもりはなかった」「携帯用ハンマーは拾ったもので使い方も知らない」と主張しました。
被疑者は起訴され、裁判でも同様に主張し、器物損壊や窃盗の故意を否認しました。初犯であり、車のガラスが割られたものの被害は大きくないので、常識的には執行猶予がつく事案でしたが、裁判官は「反省していない被告人に執行猶予はつけない」との考えの持ち主で、たしか懲役1年6月の求刑に対して懲役1年2月の実刑判決が言い渡されました。この事案は、裁判官によっては執行猶予が付くかもしれません。ちなみに、被告人は控訴し、控訴審では、被告人は一転して罪状を認めて反省していると述べたので、執行猶予付きの判決が言い渡されています。
なお、執行猶予期間中に別の罪を犯せば、執行猶予が取り消され、猶予されていた刑罰、別の罪の刑罰が合わせて科されます。「執行猶予が付いて刑務所に行かずに済む」と安堵するだけでなく、真剣に更生に努めることが必要です。