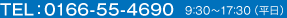北海道経済 連載記事
2025年3月号
第180回 3回目の厄年 60年ぶりの丙午
小林史人弁護士は数えで今年60歳。つまり61歳の厄年の「前厄」にあたる。今回は過去2回あった厄年、そして来年60年ぶりに巡ってくる「丙午」について考える。(聞き手=本誌編集部)
昭和41(1966)年に生まれた私は、今年60歳(数え年、以下同じ)。前厄に当たります。厄年は一生のうちに3回あるとされ、本厄は25歳、42歳、61歳で訪れます。それぞれ前年が前厄、翌年が後厄となります。女性は19歳、33歳、37歳、61歳が本厄ですが、こうした習俗に統一的なルールがあるわけではなく、神社によっては見解が違うところもあるようです。
25歳のころには「厄年」という概念にまったく関心がありませんでしたが、後から振り返れば災いが降りかかったような気がします。というのは就職活動をせずに司法試験の準備を本格的に始めたのがそのあたりで、合格まで10年かかりました。当時は合格率が2〜3%しかない旧制度の司法試験が行われており、何度も不合格と再挑戦を繰り返すのが当たり前だったとはいえ、最初の厄年できちんと厄祓いをしてもらえば、もっと早く合格できていたかもしれません。
その後、弁護士になることはできたのですが、3回の本厄のなかでも特に深刻とされる42歳の大厄を前に、41歳のころからは上川神社に毎年行って厄祓いないし除災のお祓いをしてもらっています。人の形に似せた紙(形代)に、自分の名前と生年月日を書いて、この紙を撫でてから奉納します。こうすることで人形が私の代わりに災難を受け止めてくれるとのことです。形代のおかげか、大厄ではこれといった災難や病気はなく、順調に過ごすことができました。
今年の正月もお祓いをしてもらいました。形代に数えの年齢「六〇」を書きました。昨年は心臓手術を受けるなど、すべてが順調とはいえない年でした。それが厄と関係があるのかどうかはわかりませんが、それ以上に還暦が見えてきたことのほうが感慨深く、またショックでもありました。
私たち昭和41年生まれは、女性の気が荒く、夫を不幸にするとの迷信があった「丙午」で(言うまでもなく、丙午生まれの女性が他の干支の女性と違うということは現実にはありえません)、出生数が前年を約25%下回っています。減少分の約1割は、出生届の提出を遅らせることで行われたとの推計があります。病気や天災、戦争以外の要因で出生数がこれほど減少するのは世界的にみて珍しい現象です。干支は中国、韓国、ベトナムなどにもありますが、丙午の迷信は日本以外にはありません。
私たちの学年は受験を他の学年とは違う状況で潜り抜けてきました。現在でも人口ピラミッドを見ると、私たちの年齢だけがくぼんでいます。一周前の丙午は偏見がもっと深かった明治39(1906)年生まれで、このときは多くの親が主に出生届の提出を遅らせることで丙午を回避したと言われ、出生数がやはり前年を約4分の1下回りました。
明治39年生まれで存命の人はもういません。そして来年生まれる子は60年ぶりの丙午です。迷信に影響される人はもう残っていないと思いますが、次の丙午世代がどんな人生を歩むのか、60年後の世界がどのようになっているのかに興味があります。