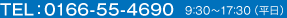北海道経済 連載記事
2025年2月号
第179回 「現代社会」が進路を変えた?
大学卒業から弁護士になるまでのルートは、司法改革の影響で大きく様変わりしたが、試験科目に注目すれば大学入試も変化を繰り返してきた。今回は高校時代の社会科の科目選択に小林史人弁護士が受けた影響を振り返る。(聞き手=本誌編集部)
1966(昭和41)年度に生まれた私たちは、丙午(ひのえうま)の迷信の影響で出生数が前後の年と比べて顕著に少なかったためか、小学校、中学校、高校に入学するたびに、当時の文部省が新しい学習指導要 領を実施しました。このため1年先輩の学年が教わっていた内容が、教科書からまるまる削られていることがよくありました。
一方で、新しい科目が登場することもありました。その例が物理・化学・生物・地学の基礎部分を集めた「理科Ⅰ」と、倫理・政経の基礎部分を合わせた「現代社会」です。高校の社会科では1年次で現代社会が必修となり、2年次以降で世界史、日本史、地理、倫理、政経から選択して履修するようになりました。私は2年次に地理を選択し、高校時代に歴史を履修しませんでした。
国公立大学の共通一次テスト(現在の大学入学共通テストに相当)には現代社会と地理で臨みましたが、国公立大学(2次試験)や私立大学に、現代社会を受験科目に加えた大学はほとんどなく、1年次必修の現代社会は、入試では共通一次でしか使えず、歴史を履修しなかったことで受験できる大学が限られました。私は歴史に興味を持っていた親の意向で名前に「史」が入っており、自分自身、歴史上の人物に興味とそれなりの知識があったため、日本史ないし世界史を履修していれば、得意科目となり入試でも武器になったものと思っています。結局、私は1年浪人して中央大学に進むことになりますが、浪人するのがわかっていれば、高校3年時に日本史ないし世界史を履修すれば良かった、そうすれば、早慶の法学部を受験でき、国立大学では最も社会科の比重(社会2科目選択)・配点が大きい東大合格も夢ではなかったのにと思うことがあります。
いまもこうした思いを抱くのは、結局、入試科目としての価値が認められなかった現代社会が必修だったために、私の人生が悪影響を受けたのではないかとの疑念が残っているためです。 現代社会を入試科目に加える大学はその後も少ないままで、2022年度の指導要領改定では「現代社会」が消え、「公共」へと変更されました。
私は、高校当時、大学受験に関する情報に疎く、高校2年生までは国立大学の2次試験の科目と配点、私立大学の受験科目と配点を知りませんでした。受験生になって、ようやく調べて分かったもので、現役合格を目指す以上、3年時に歴史を履修して受験に用いる選択はできませんでした。現在は違うと思いますが、当時は学校からも大学受験に向けたサポートもあまり行われていませんでした。前もってこうした受験情報を備えていれば、私の進路も変わっていた可能性があります。
もっとも、弁護士として扱う業務に出身大学はほとんど影響しません。多少回り道はしたものの、弁護士になることができましたし、私は現在の立場や仕事に満足しています。東大や早慶を出て四大事務所に入ったり、官僚になることもあり得たかもしれませんが、大規模案件を扱うため激務となる四大事務所の弁護士や、官僚の窮屈な仕事が性に合っているとは到底思えないので、現代社会という科目のおかげで結局は落ち着くべきところに落ち着いたと言えるかもしれません。