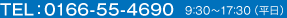北海道経済 連載記事
2025年1月号
第178回 様変わりした母校の授業
小林史人弁護士は旭川東高校全日制(35期)の卒業生。今回は、最近参観した現在の東高の授業と、40年以上前に自らが受けた授業の様子の違いについて語る。 (聞き手=本誌編集部)
私は現在、旭川東高の「学校評議員」を他の4人の委員と一緒に務めています。先日、評議員の会議が学校であり、1・2年生を中心に複数の授業を5〜10分ずつ参観する機会を得ました。評議員としてグループ討論を取り入れた授業形態の試みを参観したことはありますが、コロナの影響でそれもなくなり、高校の通常の授業を見学するのは初めてかも知れません。
どの授業でも、先生がしっかりと準備をして授業に臨んでいると感じました。生徒が予習をしてくることは想定されていないようであり、初めて触れる内容でも理解できるよう工夫がこらされていました。生徒は積極的に発言しており、合いの手を入れるような不規則発言で授業を盛り上げる生徒もいました。私が高校生のころは、教科書やノートを注視したり、ひたすら板書したりしながら、一方的に話をする教師もいました。教師の話を真剣に聞き、ノートを取っている生徒はいたものの、他の科目の勉強(「内職」)に励む生徒や、内容を理解できず置いて行かれる生徒も多くいました。私が参観した限りでは、授業は双方向型であり、内職している生徒は見当たりませんでした。また、数学の授業で教えていた内容は、約40年前よりも高度、レベルが上がっているように思います。
教師の働き方改革にからんで、部活動の重い負担がよく指摘されますが、授業の準備にかかる時間も相当増えているのではないかと思います。
ITの積極的な活用も印象に残りました。教科書にQRコードが印刷され、テーマごとに情報をウェブから取り入れることができるようになっていました。板書をスマホで撮影することも許されており、学校に携帯電話を持ち込むことの是非が論議されたのは過去の話で、いまやスマホの活用が前提になっています。
私たちのころには存在しなかった内容の授業もありました。「家庭基礎」では、男女平等や女性の社会進出についてグループ討論を行い、グループごとの結論を発表していました。かつて「家庭科」といえば料理や裁縫といった実技ばかりでしたが、時代の変化が教育にも反映されているようです。
生徒の服装にも変化がありました。東高は私たちの時代も現在も制服がなく、生徒は私服で通えるのですが、多くの生徒「着替えなくてもよい」「ラクだから」という理由で、体育の授業以外でも学校指定のジャージを着ています。その比率は、学年が上がるごとに上昇し、3年生はほとんどがジャージ姿です。私たちのころは、指定ジャージ(東とんジャン)があまりにダサかったので、体育以外で東ジャンを着ている生徒はいませんでした。また、私服だと寄り道したり、夜の街に遊びに行ったりしやすいですが、ジャージ姿だとそのようなことはしづらく、総じて今の生徒は、真面目なのだと思います。
少子化の影響で東高でもクラス数が減っています。私たちのころは1学年10クラス、現在は6クラスです。かつては男女比率が3対1程度だったと記憶していますが、現在は年によって異なり、1対1から3対2程度。40年前よりも男女比率のバランスが取れているのは良いことだと言えるでしょう。