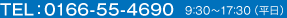北海道経済 連載記事
2024年12月号
第177回 「再審法」の改正が必要
袴田巌さんの再審公判で無罪判決が言い渡され、逮捕から58年後にようやく完全な自由の身となった。今回の法律放談は、冤罪を晴らすのにこれほどまでに長い歳月がかかった理由を考える。(聞き手=本誌編集部))
1966年、静岡県で一家4人が殺害された事件で死刑が確定した袴田巌さんについて行われていた再審公判で、9月26日に静岡地裁が無罪判決を言い渡しました。10月9日に最高検察庁が上訴権を放棄。実に逮捕から58年後に袴田さんが冤罪から解放されました。
袴田さんについては80年に死刑判決が確定し、翌年には弁護団が再審を請求し、いったんは請求を退けられたものの粘り強い活動を続け、33年もの歳月を費やして静岡地裁から再審決定を勝ち取りました。2014年からは死刑と拘置が停止されています。
もしも死刑が確定後速やかに執行されていれば、取り返しのつかない誤りとなったわけですが、幸い、刑は執行されませんでした。他の事件も見ても、冤罪の余地がまったくない死刑囚は早期に刑を執行される傾向があるように思います。当局者は袴田さんに冤罪の可能性が少なからずあると感じて刑の執行を先送りし、その結果が無罪につながったのでしょう。
いま問題視されているのが、再審に関する法律や制度の不備です。刑事訴訟法の中の再審に関する規定は435条から453条までわずか19条しかなく、再審の手続きは多くの部分が裁判所の裁量に委ねられています。また、検察が持っている証拠の開示を義務付ける規定はありません。これでは再審を求めても、その扉は開かず、徒に時間だけが経過してしまいます。再審申立人側にとってはとてつもなく高い壁があるのです。袴田さんについては、検察側が長期間、存在を否定していた証拠品のネガフィルムが静岡県警に保管されていましたが、もっと早期に存在が確認されるべきでした。
検察がなぜ再審開始に執拗に反対するかといえば、一言でいうとメンツを潰されるからでしょう。捜査や公判手続きの適正には絶対の自信とプライドを持っており、これが潰されてしまうからです。袴田さんの無罪確定を受け、畝本直美検事総長は、捜査機関による証拠捏造を認定した静岡地裁の判決理由に対して「強い不満を抱かざるを得ない」「到底承服できない」とし、袴田さんが「相当な長期間にわたり法的地位が不安定な状況に置かれてきたこと」も考慮して「控訴が相当ではない」と判断し、謝罪としては「この点については、刑事司法の一翼を担う検察として申し訳なく思う」と述べるにとどまりました。証拠捏造との認定には、かなりプライドを傷つけられたようです。
ちなみに、再審の裁判長も検事総長も中央大学出身で、私の先輩にあたります。裁判長は当時、私が所属していた専門ゼミのチューターでした。
日弁連は2019年の人権大会で再審法改正を求める決議を採択し、「再審法改正実現本部」が改正を目指して様々な取り組みをしています。袴田さんの無罪確定を受け、再審法改正の気運はさらに高まるでしょう。
10月23日には1986年に女子中学生が殺害された事件で犯人とされ、有罪判決が確定して服役、出所した前川彰司さんに対して、名古屋高裁金沢支部が再審開始を決定しました。この事件でも、捜査当局が別の事件に関与した人物に、見逃す代わりに前川さんに不利な証言をするよう依頼していた疑いが指摘されています。検察が異議を申し立てなかったため、前川さんは再審で無罪となる見通しです。厳しい批判にさらされ、検察の姿勢も徐々に変化しているのかもしれません。