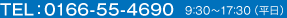北海道経済 連載記事
2024年11月号
第176回 理由が先か結論が先か
論文、レポートなど論理的な組み立てが必要な文章の作成には、2種類の道筋がある。司法試験の論文式問題も事情は同じ。今回の法律放談はこれら2つの方法に注目する。(聞き手=本誌編集部)
法科大学院を経由せずに司法試験の受験資格を得られる予備試験は、短答式(○×式)と、短答式に合格した人が進める論文式、論文式合格者が進める口述式の3段階から構成されています。私が受けた旧司法試験と同じ構成です。
論文式試験では、ある問いに対して、事実関係を整理したうえで、関連する法律、判例、学説などを紹介し、自らの考えも述べて結論をまとめます。論文を書くには2つの方法があり、うち一つが①採用する理論・理由を決め、それに従って結論を出すもの、もう一つが②常識を頼りにまず結論を出し、それから結論に至るまでの根拠を組み立てるというものです。
①の方法だと論理的正当性に重きを置いてしまいがちになるため、言及する学説が増え、前提部分に時間を費やしてしまって、肝心な部分の論述が弱くなってしまうことがあります。受験勉強の段階でも学術的になりがちで、各論点を掘り下げるため、手間と時間がかかり、効率は悪いです。また、学術上の理論に拘泥しすぎるあまり、常識から離れた結論を導いてしまうこともあります。昔の真面目な受験生は、学者の書いた本を購入し、読み込んで勉強しました。そうすると学術上の理論的対立に興味を持ってしまう結果、①のやり方で答案を書いてしまいがちで、努力の割には点を拾うことができず、なかなか合格できないという憂き目に遭います。実務家ではなく、学者として法学の研究を続けるなら①のような思考方法が適しているかもしれません。
これに対して②は常識的な結論に合わせて判例や学説を採用するためミスが少なく、また、与えられた事実や事情をあれこれ検討して、自分の出した結論を導く事実・事情を採用すれば良いので、効率よく点を拾うことができます。司法試験は実務家採用試験なので、それで良く、また、合格までの時間も短縮できるのではないかと思います。
現実の裁判においても、裁判官は②を採用し、まず社会常識に沿って判決の主文を決め、それから判決に至る理由を構成していると思われます。理論的に正しくても敗訴することがあるのはそのためでしょう。
旧司法試験では、学説の学習が現在よりも重要でした。というのは、しばしば「○○について論ぜよ」など、文字通り一行だけの簡潔な問題が出題され、十分な文字数の答案を書くためには、法律や判例のほか、通説以外の学説にも踏み込む必要があったからです。
また、学説にも学派があり、東京大学の学派が主張する学説は、少数説であっても権威があり、それで司法試験の答案を書いても良い成績がつきました。受験生の大半が、東大学派の学説を取ったので実務では少数説であっても受験界では通説だった学説もあります。
近年は一行問題が出題されておらず、現実的な事件に立脚した問題が出されており、少数の学者の唱える学説のために受験生が貴重な時間を割く必要性は低下しています。司法試験改革の是非についてはさまざまな主張がありますが、この点だけに絞れば司法試験は「進歩」したと言えそうです。