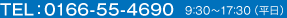北海道経済 連載記事
2024年10月号
第175回 もはや予備ではない予備試験
弁護士、検察官、裁判官(法曹三者)になるには、司法試験に合格しなければならない。最もオーソドックスなルートは法科大学院だが、法科大学院を経由しない「予備試験」というルートへの注目度は高まる一方。今回は小林史人弁護士の個人的な経験も踏まえて予備試験に注目する。 (聞き手=本誌編集部)
私が受けた旧司法試験制度には、難しすぎて多くの受験生が膨大な時間を費やしている、民間の司法試験予備校の力に頼る傾向が強いといった批判の声がありました。新司法試験はこうした問題を解消することを目指していました。旧司法試験の合格率が1〜3%程度であったのに対し、新司法試験の合格率は45・34%(2023年)。もはや運次第で合否が決まる一発勝負ではありません。
しかし、法科大学院にも問題があります。資力に劣る学生や資力があっても忙しい社会人は、たとえ能力が高くても、法科大学院を経由して新司法試験に合格するのは困難です。このため2011年、「司法試験予備試験」(いわゆる予備試験)を合格した人は、法科大学院を卒業した人と同じ程度の学力があるとみなし、司法試験を受験できる制度が設けられました。
ところが、名目上は「予備」であるはずのこのルートが、優秀な法曹を養成するための有力なルートとなっています。決して簡単な試験ではないのですが、法科大学院に在学中、または大学に在学中から、学歴を問わない予備試験に挑戦して、法科大学院卒業より何年も早く、司法試験受験資格を得る人が増えています。
学校別で予備試験の合格者数(2023年度)を見れば、東京大が103人。以下、慶応大46人、京都大26 人、中央大25人、早稲田大22 人など、司法試験の有力校が続いています。いま、法曹を目指す学生の間には、早くから予備試験を受けて、合格できない場合に法科大学院に進む人が増えています。予備試験合格なら法科大学院に費やす時間と学費を節約できます。
ちなみに、最終学歴が高卒以下(卒業、中退、在学中)で合格した人は4人だけ。大学や法科大学院に行けなかった人にも門戸を開くという役割を、予備試験はほとんど果たしていません。
法科大学院を修了した人も、予備試験を合格した人も、(新)司法試験を受ける必要があります。合格率は法科大学院出身者が40・67 %(修了者32・61%、在学中59・53%)であるのに対し、予備試験合格者は92・63%となっています。法科大学院修了者の合格率が一番低く、法科大学院の存在意義が問われる結果となっています。
さて、私事なのですが東京大2年生の息子が、今年7月に行われた予備試験の短答式試験に合格しました。東京大は1、2年時が「前期課程」とされ、大学ではもっぱら教養科目を学び、法律科目はほとんど学びませんが、司法試験予備校の参考書を買って半年ほど勉強してみたところ、合格できたそうです。私が旧司法試験の短答式に初めて合格したのは大学を卒業して3年目であり、時間にして3年半を要しました。試験の難度が違うとはいえ、驚いています。
予備試験は旧司法試験と同様、合格のためには論文式試験、口述式試験をパスしなければなりません。私の場合、短答式に合格してから、さらに7年半を要しています。まだ、手つかずの科目もあるようですし、今年度に予備試験に合格することはさすがに無理だと思っています。