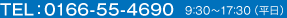北海道経済 連載記事
2024年8月号
第173回 人権擁護委員会の「勧告」
紛争解決基準は、判決という形で裁判所が示すものであるが、ときには申立てを受けて弁護士会が調査を行い、人権侵害を行った団体等に勧告することがある。今回の法律放談は弁護士会に設置されている「人権擁護委員会」の活動について。(聞き手=本誌編集部)
旭川弁護士会に設置された人権擁護委員会が6月21日、旭川市内のある町内会に対して、町内会の一般会計から上川神社・北海道護国神社への支出をやめるよう勧告しました。
当該町内会の会員から人権救済の申し立てが行われたことを受け、人権擁護委員会が申立人と町内会の双方に対して調査を行いました。その結果、町内会の一般会計から神社への支出は違法であるとの結論が出たわけです。ただし、勧告に裁判の判決のような強制力はありません。当該町内会がどう対応するのかは当該町内会次第です。
申立人が問題視した町内会の行為は2つあります。まず、回覧板で神社の神札購入を希望する人を募り、班長にとりまとめさせて集金させ、購入した神札を配布させたこと。もう一つは、町内会の一般会計から神社への支出を行ったことです。
過去には行政による神社への「玉ぐし料」の支出の是非が争われた裁判で、こうした公権力による支出は、憲法20条の定めた「信教の自由に抵触し違憲である」との判決が出されたことがあります。一方、町内会は任意団体であることから、憲法の直接適用はできませんが、団体の行為の態様・程度が社会的許容限度を超える場合は、民法90条(公序良俗)等の条文を憲法の趣旨を踏まえて解釈して違法となる場合があるのです(憲法の間接適用)。争点のうち回覧板で神札購入を募ったり、班長に注文のとりまとめ・集金・配布をさせたりすることは、会員の信仰の自由や班長の宗教的行為の自由を侵害するおそれはあるものの、人権侵害行為として違法とまでは言えないとして、勧告を見送りました。一方、町内会の一般会計からの神社への支出については、町内会はその地域のために公的活動を行い、その活動に対して市から一定の支援があることなどを考えれば、町内会には一定の公共的性格があること、町内会への加入・町内会からの脱退の自由が大きく制約されており、任意団体であるものの、強制加入団体に準じることから、支出は違法、勧告相当と判断しました。
憲法が守ることを定めた人権はさまざまなものがありますが、信教の自由は精神的な自由であり、財産権等と異なり、よほどの事情がない限りは制限できないとされています。町内会の決算書に「奉賛金」と書かれていた年度もあり、神社に対する寄付であると判断しました。
この制度では、人権擁護委員会が調査結果に応じて、人権侵害があると認定すれば「勧告」を、人権侵害を断定できないもののそのおそれがあるものについては「要望」を行います。人権侵害が認められなかったものは「不処置」となります。
旭川弁護士会に対する人権侵害の申し立ては大半が刑務所内での処遇に関して受刑者から行われるもので、その数は年間5件程度です。このうち「要望」は1年に1〜2件程度、「勧告」は2年に1〜2件程度で、調査の途中で見込みを聞いて申立人が取り下げることも少なくありません。
弁護士法第1条には弁護士の使命として「人権擁護と社会正義の実現」が明記されており、人権擁護活動は最も基本的かつ重要な活動です。そのため人権擁護委員会は、弁護士会の数ある委員会の中でも、最も長い歴史を有しています。