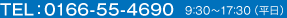北海道経済 連載記事
2024年5月号
第170回 氏名秘匿で国選弁護困難に?
刑事裁判では被害者の氏名なども明らかにされるが、こうしたしくみが性犯罪等の起訴を難しくしているとの反省から、被害者の情報を秘匿できる制度が導入された。他方で、この新制度のために、弁護活動に支障が出る上、国選弁護を受任する弁護士が減少するとの懸念もある。(聞き手=本誌編集部)
改正刑事訴訟法がこの2月15日に施行されました。改正の大きなポイントは、性犯罪等に関して、被告人側に渡される逮捕状や起訴状などの書類に被害者の氏名を記さないことが可能になったということです。
これらの書類には、犯罪の事実を明確に記すのが原則です。そこには、被害者の住所や氏名も含まれます。
しかし、性犯罪等の多くでは、被害者と加害者の間に面識がありません。被害者の中には裁判の書面を通じて氏名が加害者側に伝わり、将来報復されるのではないかとの不安から被害届の提出や捜査への協力をためらう人もいます。実際に2012年に発生したストーカー事件では、警察官が逮捕状を読み上げる際、被害者の結婚後の名前や住所も犯人に伝えていました。この事件では犯人が市役所からも被害者の情報を入手し、のちに被害者は殺害されています。
従来制度でも、裁判所は被害者の名前を被告人の弁護士に開示する際、被告人本人には明かさないとの条件を付けることができました。新制度の下では、裁判所が被害者に危害が加えられる恐れがあると判断すれば、被告人・被告人弁護士に被害者氏名を伏せたまま裁判を開けるようになります。
現在、性犯罪等のうち起訴に至る事件は約3割程度であり、被害者の個人情報が守られれば、この比率が上昇することも考えられます。他方で、被害者の氏名が秘匿されるために、弁護活動にも支障が出ます。被害者側の行動が犯罪の要因になった可能性があったとしても、弁護士が裁判でそれを証明することが非常に困難になってしまいます。「被害者の氏名秘匿の結果、えん罪が増えてしまう」と懸念する声もあります。
もう一つ懸念されることは、国選弁護を引き受ける弁護士が減少する可能性です。被害者が誰かわからなければ、「被害者側の人間と面識がある」「別件で過去に相談を受けたことがある」など、何らかの関係がある弁護士が被告人の弁護を引き受けてしまうかもしれません。通常、被害者と何らかの関係があり、被告人の弁護を担当することが「利益相反」に該当する可能性のある場合は、被告人の弁護を引き受けることができません。何百万人もの人が暮らす大都市ならともかく、旭川や道北の小規模な自治体では、匿名の被害者が実は知人だったということもあり得ます。
以前にも述べましたが、国選弁護を引き受ける弁護士の数は決して十分ではありません。盆や正月、連休の時期に休日当番弁護の担当日が指定されると、事件が配転されることを前提にして行動しなければならず、盆や正月、連休の時期に旅行や帰省をすることができなくなります。これを避けるため、国選弁護を扱わない弁護士もいます。今回の刑訴法改正で、国選弁護の引き受け手がさらに減るかもしれません。凶悪犯罪の被疑者も、弁護人を付されて適正な手続きで裁判を受ける権利を憲法で保障されていますが、国選弁護の引き受け手が見つからなければ、この権利も骨抜きとなります。