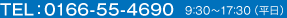北海道経済 連載記事
2024年3月号
第168回 「オンライン接見」の必要性
道北地方の刑事弁護を担当する弁護士たちにとり、冬は過酷なシーズンとなる。今回は小林弁護士が、1月初旬に被疑者との接見のため稚内に4回通い、音威子府・中川間の山間部を通行した経緯をふまえ、導入すべきとの声が高まっている「オンライン接見」について解説する。(聞き手=本誌編集部)
「当番弁護士」という制度があります。罪を犯した疑いで逮捕された被疑者が無料で1回弁護士に来てもらって、相談し、アドバイスを受けることができる制度です。
いつ刑事事件が発生し、当番弁護士の要請があるかは、事前にはわかりません。そこで、担当希望者に当番弁護士名簿に登録してもらい、登録名簿に沿って当番弁護待機日を割り当て、事件が発生し当番の要請があった日に待機している弁護士(複数の事件が同じ日に発生する可能性に備え、「主待機」と「副待機」がいる)が接見に行くシステムにしています。当番弁護士は旭川市内当番と旭川市外当番があり、市内当番は1日ごとに弁護士を割り当てますが、市外当番は1週間単位で割り当てます。そのため、市外当番の場合、逮捕された被疑者が勾留されたときも待機日が継続している場合は、裁判所から被疑者国選弁護人に選任され、当番弁護士で担当した被疑者を引き続き、担当することになり、勾留期間中の長距離接見を余儀なくされます。
今年の1月4日から一週間、私は旭川市外の当番(主待機)でした。初日に旭川弁護士会から、「稚内で刑事事件が起き当番弁護士の要請がありました。担当できますか」と電話連絡が入りました。遠方だからというのは断る理由にならないので、担当せざるを得ません。
稚内までJRで行くという選択肢もありますが、旭川駅で午前9時発に乗車しなければ日帰りできないという時間的な都合などの理由のため、車で行かざるを得ません。とはいえ、旭川・稚内間の距離は往復約500キロ。天候によっては命がけになります。とくに神経を使うのは音威子府・中川間の山間部です。稚内での接見を終えた後は、なんとか日没前にこの難所を通過したいという気持ちですが、夜間の通過を余儀なくされることもあります。
結局、私は当番弁護士として1回、勾留期間中に国選弁護人として3回、旭川・稚内間を往復しました。悪天候のため音威子府まで行って引き返したことも1回ありました。
こうした事情は弁護士会ごとの担当エリアが広い道内だけではなく、離島のある道外の地域でも同じです。このため日本弁護士連合会が導入を求めているのが、リモート会議のように、ネット回線やカメラ、マイクを使って行う「オンライン接見」です。実現すれば、弁護士が遠方の施設まで足を運ばなくても、被疑者と話すことができるようになります。
現在も、旭川の警察署の接見室から稚内の警察署に電話をかけて被疑者と話すことはでき、私も利用しましたが、これは刑事訴訟法が「立会人なくして接見することができる」と定めた接見交通権の行使ではなく、秘密が保障されていません。遠くまで車を走らせ、対面で接見するのはそのためです。
オンライン接見については、現在、法務省法制審議会において、刑事手続全般におけるIT技術活用の一部として論議が続けられています。正式な接見交通権の行使と位置づけ、秘密を保障することが導入の必須条件となるでしょう。