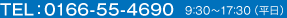北海道経済 連載記事
2023年12月号
第165回 中央大学 巻き返しなるか
司法試験のたびに報道されるのが法科大学院別合格者数ランキング。昭和の旧司法試験では強さを発揮した中央大学は苦戦が続く。今回は小林史人弁護士が母校・中大のかつての隆盛、現状、今後の希望について語る。(聞き手=本誌編集部)
令和4年度の法科大学院別司法試験合格者ランキングを見ると、1位は京都大学(法科大学院、以下同じ)で119人、これに東京大学の117人、慶応義塾大学と早稲田大学がいずれも104人で続いています。私の卒業した中央大学は50人。全体で8位、私学では3位でした。
かつて、法曹の世界における中央大学の存在感は圧倒的でした。昭和45年度まで20年間合格者ランキング首位で、昭和40年度まで中大から年間150人以上、東大の合格者の2倍超の合格者を輩出している状況でした。中大は通常の法学部のカリキュラムとは別に、司法試験を目指す学生たちの受験サークルである学術研究団体が数多く活動しており、団体ごとに蓄積した受験ノウハウの伝授と、先輩実務家の手厚い指導を受けることができ、いわば司法試験予備校が学内に数多く存在し、他大学が司法試験に興味を示さなかった時代は完全に独走状態でした。
その後、東大や早稲田も司法試験の指導に力を入れ始め、中大のかつての優位は失われました。バブル景気崩壊後は京大や慶應も司法試験に参入しました。4年間、大学の学部で学んだあと、法科大学院で2〜3年専門的に法律を学んで試験を受ける現在の制度でも、中大は苦戦しているように見えます。
しかし、実際には中大は相変わらず、法曹界に人材を多数供給しています。前記の通り、22年度の中大法科大学院からの合格者は50人でしたが、中大を卒業し、他の大学の法科大学院に進学して、司法試験に合格した人も含めれば140人に達します。つまり、中大で司法試験の受験指導を受けた人が、他の大学の法科大学院に進んで司法試験に合格しているのです。プロ野球でいえば地道に育成した選手が他球団にFA移籍して活躍するようなものです。
これは、学生の「大学のブランド志向」が法科大学院選択にも及んでいることが原因です。東大京大はもちろん、早慶を蹴ってまで中大を選択する学生がいないのとほぼ同じことが法科大学院選択でも起こっているのです。この業界に中大のOBOGが多いのは事実ですが、法科大学院も中大を選択するほどの中大ファンではないのです。
もう一つ、中大の法学部が昨年度までキャンパスを都心から離れた東京都八王子市に置いていたために、優秀な学生が中大を敬遠して他の大学に流れているとの指摘があります。都心回帰の傾向を強める他の私大と同様、中大も今年度から法学部を都心の茗荷谷に移転しました。これで大学ブランドが向上し優秀な学生が集まれば、数年後にはその効果が表れるかもしれません。しかし、中大の問題は学部ではなく法科大学院にあり、その法科大学院は今年度から駿河台、それ以前は市ヶ谷で都心にありました。中大法学部の移転で法科大学院にも優秀な人材が集まるというのは楽観的すぎると思います。
中大卒の合格者は、現在でも多く、中大が司法試験受験指導に定評があることは今も昔も変わりません。私などは中大に進学していなかったら、合格していないでしょう。中大卒の法曹の1人として、中大が法曹育成能力を発揮して巻き返すことを願っています。