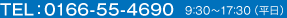北海道経済 連載記事
2019年1月号
第106回 養育費の引き上げについて
離婚の際の養育費決定の根拠である「養育費算定表」が見直されることになった。シングルマザーの困窮を緩和するために養育費が引き上げられる可能性が大きいが、小林史人弁護士は、養育費を払う側の負担も重いことを指摘する。(聞き手=本誌編集部)
離婚の状況はさまざまで、夫・妻の収入、子の数と年齢などはケースごとに異なります。基準がないと養育費の算定に時間がかかるため、2003年に裁判官の有志が「養育費算定表」をまとめ、現在、どの家庭裁判所でも養育費を決定するときにはこの表を基準にしています。
最近、この算定表の見直しを最高裁司法研修所が見直そうとしているとの報道がありました。2019年の5月ごろにまとめられる報告書に、養育費の増額が盛り込まれるのは確実な状況です。
近年、シングルマザーの困窮が社会問題になっています。2015年の調査によれば、母子世帯の平均年間収入は243万円で、同居している家族の収入を合わせても348万円。児童のいる世帯全体の平均所得の半分に満たない水準で、母子世帯と両親のいる世帯の間では教育水準にも差が生じています。このため日本弁護士連合会は、現在の算定表では受け取れる養育費が少なすぎるので、増額が必要と主張してきました。
算定表は、養育費を支払う側の年収、受け取る側の年収、子供の数と年齢をもとに、養育費の金額がわかるしくみになっています。たとえば7歳と10歳の子がいて、養育費を支払う側の年収が715万円、受け取る側の年収が202万円と仮定すると、子1人あたりの養育費は4万円、合計8万円となります。これは「参考資料」に過ぎず、強制力はありませんが、離婚の調停や裁判の現場ではこの算定表に従って金額が決定されています。
では、養育費が引き上げられればどうなるでしょうか。多くのケースでは元夫が養育費を払っていますが、弁護士として多くの離婚に関わってきた立場から言えば、十分な収入があり、「軽々と」養育費を払える男性はごく僅かです。専門学校や大学の授業料などは父母の収入に割り付けて養育費とは別途に負担することもあり、特に元妻の収入がない場合には、これらの捻出は重い負担となるのが通例です。養育費等の負担は親の義務であり、支払うのは当然ですが、現在以上に負担が重くなると支払いが非現実的となり、元夫が支払わなかったり、経済的に破たんするケースが増加するでしょう。少数ながら元妻が養育費を負担するケースもあり、その場合には元妻が重い負担に苦しむことになります。
また、現在の算定表は給与所得2000万円、自営業者の年収1409万円が上限となっており、上限を超える高額所得者については養育費の算定基準はありませんが、ほぼ同じ基準で算定されるので、収入が増えれば、養育費も増えていくことになります。このしくみが適切なのか疑問ですし、離婚が成立していない場合は配偶者の生活費も支払うので養育費と合わせて支払い金額が計算上は年額1000万円に達するケースもあります。
なお、借金の返済ができなくなり、自己破産する人がいますが、養育費は免責されません。離婚したい一心で高額な養育費の支払いに安易に同意する人もいますが、長期間(子が社会に出るまで)にわたり破たんすることなく負担できるのかどうか、よく考えて交渉するべきです。