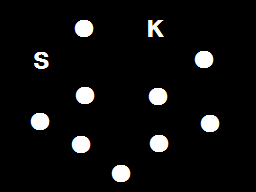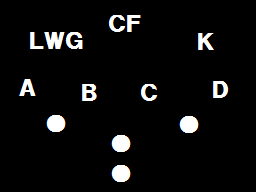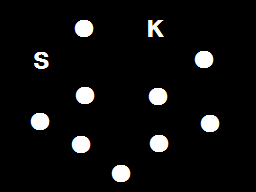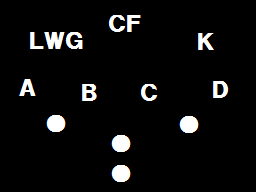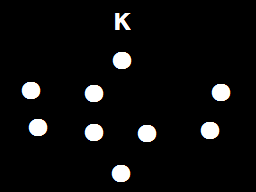独断戦術論
全て独断。定量的な検証実験による裏づけはない。
<独断01:試合前のロッカールームでの選手の様子で内部パラメーターを推測できる>
- まず、大前提として選手のモチベーションとロッカールームでの選手の様子は相関している。
- 選手のモチベーションが押しなべて低い場合、選手全員がベンチに座り込んでいて、立っている選手はいない。ゲーム1年目や年始のプレシーズンマッチでよく見られる光景である。
- 逆にモチベーションが高い場合、殆どの選手が立ち上がり、その場ダッシュなりストレッチなり、選手間の話し合いなりをしている。
- 一度など、勝利ボーナスを1億に設定した途端に、これまで画面で座り込んでいた選手がスックと立ち上がり、体のストレッチを始めたことがある。ただし、これほど分かりやすい例は滅多にない。
- 選手のモチベーションが表示上は高いのに、ロッカールーム画面で椅子に座り込んでいるときは要注意。前年度の活躍や連戦疲労により、個人レベルで通常では目に見えない「燃え尽き」状態にあると思われる。このような選手は試合に出しても、大抵はモチベーションや能力の割に活躍しないことが多い。
- 私の場合、こうした選手は思い切って1〜2週間ベンチ外にして、リフレッシュさせるようにしている。
- 追記:天皇杯を勝ち進み、チーム全員のモチベーションが高い中、準決勝でSB伊東が怪我をしてしまった。決勝の日、伊東はモチベーション最高だったが、怪我は抱えたままの状態。試合前の選手控え室では、選手達が立ってウォーミングアップする中、ただ一人伊東だけが椅子に座ったままであった。
→ このことから、試合前の選手の様子はコンディションも考慮されていると思われる。
<独断02:ハーフタイムに入る際にどちらがボールキープしていたかで後半戦の行方が占える>
<独断03:流れの中からのキーマンのシュート機会は減る>
<独断04:キーマンの逆サイドに配置した選手のシュート機会が増える>
前に挙げた独断の続きになるが、キーマンのパス→つなぎのパス→シュート!という過程の中でサイドが変わることが多いため、必然的にキーマンと逆サイドに配置した選手のシュート機会が増える。
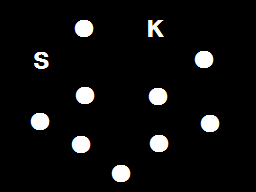
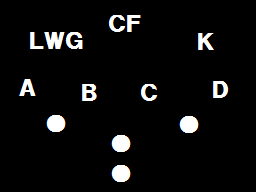
上図の「K」をキーマンとする。左図の場合、顕著に左SMFの位置「S」選手のシュート機会が増える。このため、「S」選手には攻撃的でシュート精度の高い選手を配置した方が良いことになる。
右図の場合、LWGもさることながら、左SMFの位置「A」選手のシュート機会が如実に増える。また、同じセントラル・ミッドフィールダーでも「B」選手の方が「C」選手よりもシュート機会の増える傾向にある。
<独断05:GKの攻撃力は意外に重要>
能力の高いGKを起用した場合、GKから一気にキーマンにパスする確率が高くなる。ここの「能力」とは、キック力に関連するのか、攻撃意識に関連するのかは今後要調査。GKの能力によって、
・SMFの選手にすら直接パスを出せない(パスの届かない)GK
・SMFまでは直接パスを出せるが、WGまではパスの出せないGK
・一気にWGの選手にまで直接パスの出せるGK
…など、差が出ているように思う。
<独断06:自チームの選手が退場したら、適切な戦術変更により勝率は逆に上がる>
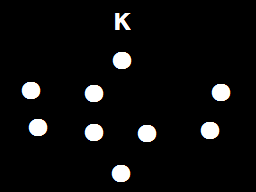
- 上図のように4-5-1(2V)カウンターにして、1人減った部分をDMに廻して、CFをキーマンにすること。一気に形勢逆転して面白いほど勝てる。勝率は8割を下らないのではないだろうか。サイドの選手は低い位置に配置するのが良いと思われる。
- キーマンはOMの選手でも良いかもしれない。決定力の低い選手がシュートする機会が少なくなる&守備が強化される、ために強くなるのか?
<独断07:ここ一番に向けた特定戦術の温存が超有効>
- 特に「アルビセレステ」「ゲルマン魂」でこの効果を実感している。
- 数ヶ月のスパンでずーーっとこのチーム戦術を封印しておいて(できればシステムも戦術も普段から避けているとさらに良い)、大舞台で劣勢になったときに満を持して使用すると、面白いほど圧勝ペースになれる。
- 例えばアルビスレステを温存する場合、3−4−3(1V)も中央突破もずっと使わないで温存しておく。普段は4−4−2(2V)ラインのサイド突破/カウンターと、4−5−1(3V)カウンターを対戦相手によって組み合わせるなどして、アルビセレステとはある程度かけ離れた布陣・戦術にするとより効果的。
- 温存戦術の使用は1回目は抜群に効果的、2回目もある程度効果があるが、3回目からは怪しくなる。
<独断08:前年度得点王、世界最優秀選手は活躍しにくい>
<独断09:留学帰りの年とその翌年は活躍のチャンス>
<独断10:30過ぎのベテランは4〜5試合に1度だけの出場だと活躍できる>
<独断11:序盤(1〜4節)に自チームの躓いた相手チームに補正がかかり、優勝争いの相手になる>
上のような独断を書くと、反論として「単純に強い(勢いのある)チームと対戦して負けただけでは?」と思われるだろうが、実感としてはそうではない。
自チームに勝ったことで、相手チームに補正がかかり、そのステージ(1stステージ、2ndステージ各々の中だけ)で躍進するように感じる。
<独断12:年初のプレシーズンマッチでは選手の警告・退場が増える>
<独断13:「ファールしやすい選手」は存在する>
- 独断12で挙げたように、プレシーズンマッチや海外遠征では選手の警告・退場が増える傾向があるため、それ以外のリーグ戦での試合に限って考える。
- 具体名を挙げれば、千葉のDM佐藤勇人、FC東京の今野などがよくファールをしている。統計を取ってみれば、より傾向は明らかになるはず。現在ざっくりした統計調査を開始しているところ。
- なお、9月上旬に選手と面会するとファールしやすさを選手が口にしてくれるが、これがどれだけ試合に反映されているかは不明。
実感としては、ここでのコメントは実際の試合とあまり関係ないように思える。
- 例えばS級DM五十嵐が育ちきった状態でも『そのファウルがチームに益をもたらすものなら、数を気にすることはないと思いますよ。』と言う一方で、同じ口調型のザコ選手は『やらずもがなのファウルって必ずありますからね。である以上、意識すればファウルは減らせますよ。』とコメントする。
<独断14:SBやCBのパス能力の低さがボトルネックになる>
- 珍しく自チームのCBがドリブルで持ち上がった際、あっさり相手選手にパスカットされてカウンターをくらう場面は頻繁に目にすることだろう。
<独断15:1シーズンでの活躍具合の上限がある>
- 序盤から絶頂期の鬼やバステンをFW起用しても1シーズン20〜30点ほど。同時期にFW東条や水口、エマーリロが好調な年でも、同様に1シーズン20〜30点ほどを稼いでくれる。鬼やバステンだから50点や60点取るかというと、全くそのようなことはない(ただし1〜3年目といった最序盤を除く)。
- これは序盤に限ったことではない。ゆえに、独断15のようなことが言えるのではないか。
- これを逆手に取ると、大量得点/失点で試合の決まった場面で得点源を引っ込めたり、守備のポジションに廻したりして、勝ち点に直結しない得点を防ぎ、活躍場面を大事な試合に取っておく、ということが有効ではないか。
<独断16:試合に出場させずに休ませることがとても大事>
- 週に1試合出場させていると、選手は疲弊してくる。週に2試合出場させていると、疲弊は甚だしい。この疲弊は、試合に出場しないと回復していく。
- 例えば、新しい年になって一度も試合を行わず(ただし試合形式の練習は適度に行って試合勘は取り戻しておく)、3月あたりに初めて試合を行ってみる。全選手が疲弊ゼロの状態で試合に臨むため、5−0くらいで圧勝できる。次の試合でもそれほど疲弊していないため、圧勝できる。
- 神レベルのDFをずーーーーっと連戦出場させてみる。試合はダイジェストで全て見るものとする。ダイジェストの中で、そのDFがファールを犯すのは、ほぼ必ず連戦で5試合目以降である(ここの5という数字はちょっとした目安でしかない)。稀に気負いすぎて?1試合目でファールすることはあるが、2〜4試合目くらいではファールすることはまずない。
- このため、DF選手を5〜6試合連戦出場させたら、疲弊によるファールを防ぐために1〜2試合を完全休養するようローテーションを組んで
- ずーーっと数ヶ月干していたGKを久々起用してみる。するとダイジェストで試合を見た際に、連戦使用していた場合とは明らかに多い頻度で、そのGKが守備でキャッチなりパンチングなりをする場面が挿入される。
- もっとも、このセーブのすぐ後で相手コーナーキックになり、ここで失点する場合も多いのだが、明らかに活躍場面の登場回数でいうと久々起用の方が多くなっている。
- この『活躍場面登場回数の増加』が単に場面増加に留まるものではなく、本当に統計学的に失点の減少や獲得勝ち点の増加に繋がっているかは、要検証。
<独断17:キーマン、プレースキッカー、戦術システムは固定しすぎないのが大事>